非定型うつ病の特徴と5つの症状



楽しいことがあってもなくても気分が滅入ったままの従来の《うつ病》に対し、良いことや楽しいことがあると気分がよくなる《非定型うつ病》というタイプのうつ病があります。マスメディアなどに多用される《新型うつ》や《現代型うつ》と混同されがちな非定型うつ病は、世間の人のうつ病の一般的なイメージからかけ離れた症状をもつことから、仮病を疑われたり、怠けているだけではと誤解されたりしがちです。
しかし、非定型うつ病は従来のうつ病と同じように患者本人は大変苦しい精神疾患です。
この記事では、主に従来のうつ病との違いに焦点を置き、非定型うつ病の特徴と症状などを解説します。
非定型うつ病とは
うつ病のうち、従来のうつ病(メランコリア型うつ病)とはかなり異なる特徴を持つタイプを《非定型うつ病》といいます。非定型うつ病は、世間の人の《うつ病》の一般的なイメージからかけ離れた症状をもつことから、仮病を疑われたり、怠けているだけではと誤解されたりしがちです。
「非定型」という言葉には、本来は珍しいという意味も含みますが、非定型うつ病の実態はそれほど珍しいものではなく、うつ病患者のうち、18~36%くらいにみられるといわれています。
マスメディアを中心に、非定型うつ病は、《新型うつ》や《現代型うつ》と区別なく扱われることがよくあります。新型うつ・現代型うつは主にマスメディアが使う言葉で、医学的な用語ではありませんので、うつ病と診断されない状態のものも含まれています。
新型うつ・現代型うつが学術的に言及される場合は、うつ病と診断されない状態に限定して用いられる場合もあるようです。
この記事では、以降は《非定型うつ病》に限定し、《新型うつ》や《現代型うつ》については、これ以上触れません。
非定型うつ病の特徴
まず従来の《うつ病》について簡単に述べます。
従来のうつ病は、《大うつ病》や《定型うつ》《メランコリア型うつ病(メランコリー型うつ病)》などとも呼ばれます。世間一般の、「真面目な人がかかる、気分が激しく落ち込んで何もできなくなり、時に自殺してしまう」イメージは、このタイプのうつ病が当てはまります。
定型うつ病も非定型うつ病も、長期間の抑うつ的な気分(悲しみや絶望感)を伴う点では変わりありません。しかし、定型うつ病ではポジティブな出来事があってもずっと落ち込んだままですが、非定型うつ病ではポジティブな出来事には(一時的に)気分が改善するという違いがあります。
その他、以下のようなものが非定型うつ病の特徴といえるでしょう。
- 慢性化しやすい・再発しやすい
- 女性に多い(2~3倍)
- 若年(10代)に発症しやすい
- 対人関係で拒絶への極端な過敏さがみられる
- 不眠や食欲不振よりも、過眠・過食がみられやすい
- 重度の倦怠感に見舞われる
なお、非定型うつ病と診断された人も、常に非定型的な症状が持続しているとは限らず、従来的な症状との間で行ったり来たりすることもよくあります。むしろ、この症状の揺れがある方が一般的であり、一貫して非定型的な症状を示す方が少ないようです。
非定型うつ病の5つの症状
非定型うつ病には、以下に示すような特徴的な5つの症状があります。
1.気分の反応性
定型うつ病では良い出来事にも悪い出来事にも反応が鈍く、常に気分が落ち込んだままですが、非定型うつ病では、良い出来事があったときには気分が改善します。良い環境が続いている間は、より長期間、正常な気分が続くこともあります。
この症状は、仕事中は落ち込みが強く暗く沈んでいるのに、週末には元気よく遊ぶことができる、というような現れ方をします。この状態を見た人からは、甘えやわがまま、怠けていると誤解されることがありますが、これは非定型うつ病の症状の1つです。
2.拒絶過敏性
《拒絶過敏性》とは、他人から拒絶されることを心配・予測、すぐに察知し、過剰に反応する傾向のことです。抑うつのある時もない時も生じ、抑うつのある時は悪化することもある性格特性です。この特性が非定型うつ病の本質であるという考え方もあります。
挫折や批判を極度に恐れ、それらに過剰な反応を示し、人間関係を避けたり、相手からの一言を誤解したり、曲解したりし、誤った内容を思い込んでしまうこともあります。
下にいくつか例をあげます。
- 仕事のミスを上司に指摘されたときに、「自分を否定された」と過剰に落ち込む、あるいは逆切れして攻撃的になる。
- 友人や恋人が忙しく時間が取れないだけなのに、「自分は嫌われているのでは」と過剰に悩み、あるいは怒り狂って攻撃的になる。
- 配偶者が「今日のごはん、おいしいね」とほめたつもりが、「いつもはまずいと思っているのか」と思い込んで落ち込む、あるいは反発して攻撃的になる。
- 配偶者が「そんなにつらいなら仕事をやめてしばらく休むといいよ」とフォローすると、「私の仕事なんて大して意味がないって思っている」と邪推して落ち込む、あるいは怒り出して攻撃的になる。
これらの反応は、周囲にとっては不快なもので、関係性に影を落とすことが少なくありません。周囲が患者を自己中心的、身勝手、わがままと評価する原因になります。
3.過食
はっきりとした食欲増進や体重増加があります。食事の量が明らかに増え、体重が増加します。
4.過眠
睡眠時間が長くなります。夜間の睡眠と日中の居眠りの合計時間が10時間以上の日が、週に3日以上の場合に過眠と判断されます。これは抑うつの無い時の睡眠時間が8時間と仮定されているので、普段より2時間以上睡眠が増えている日が週に3日以上の場合に過眠と判断されます。
5.鉛様の麻痺
通常の疲労感を超え、手や足が鉛のように重い感じがする状態です。まるで肩からおもりがぶらさがっているような感じで、起き上がることも、いすから立ち上がることもつらい状態です。
上の5つ以外にも、「過去のつらいことを思い出し、感情のコントロールができなくなる」「午後から夜間にかけてうつ状態が強くなる」なども非定型うつ病でよくある症状にあげられます。
定型うつ病と共通する症状
非定型うつ病は《大うつ病》のサブタイプ(下位分類)なので、従来のうつ病と共通する症状もたくさんあります。
例えば、以下のような症状が当てはまります。
- 悲しみやむなしさを感じる
- 落ち着かず、イライラする
- 疲れ切り、何もする気力が湧かない
- 自分が悪い、自分には価値が無いと思い込む
- 死にたいと思う、あるいは死や自殺について考える
非定型うつ病の治療法
治療法は定型的なうつ病に準じます。
以下のような治療法があります。
- 休養・環境調整
- 薬物療法
- 精神療法・心理療法
- 電気けいれん療法(ECT)
- TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
非定型うつ病との向き合い方
非定型うつ病は再発しやすいので、生活を見直してできる限り再発を抑え、健康な時間を取り戻しましょう。
- 規則正しい生活を送る:規則正しい生活の基本は、就寝時間と起床時間を毎日守ることです。
- 身体を動かす:適度な運動は夜の寝つきをよくするほか、メンタルの改善にも役立ちます。
- 健康的な食事を取る:栄養バランスを考えた食事を、毎日決まった時間に食べます。特に朝食が重要です。
- 周りの助けを得る:家族や友人など、周囲と良い関係を築くように努めましょう。あなた自身が気付くよりも、先にあなたの異変(再発の兆候など)に気付いてくれる可能性もあります。
併存・合併しやすい精神疾患
非定型うつ病は他の精神疾患が合併することも多々あります。
代表的なものとして以下のような疾患があげられます。
- パーソナリティ障害
- 不安障害
- 摂食障害
- 双極Ⅱ型障害
- 物質使用障害(アルコール依存症など)
いつ医療機関に行けばいいのか?
うつ病は、定型・非定型に関係なく本人、そして時に周囲の人にとってもつらい精神疾患です。
気分が落ち込み、疲れ切って気力がわかない、不安や焦燥感が強い、睡眠や食欲に異常があるなど、日常生活に支障をきたしている場合はうつ病を発症している可能性があります。従来のうつ病や、非定型うつ病の症状があると思った場合は、すぐに精神科・心療内科を受診してください。
いきなり医療機関に行っていいのか迷ってしまうような場合は、セルフチェックなども有用でしょう。
もちろん、迷ったままのご来院でも問題ありません。そのような方は大勢いらっしゃいます。うつ病は早期発見・早期治療がとても大切です。何も手立てをしないことで、それだけ苦しむ期間が長くなります。
まとめ
従来の《うつ病》ではポジティブな出来事があってもずっと落ち込んだままですが、《非定型うつ病》ではポジティブな出来事には(一時的に)気分が改善します。他にも「拒絶過敏性」「過食」「過眠」「鉛様の麻痺」などの特徴的な症状をもちます。
非定型うつ病はパーソナリティ障害・不安障害・摂食障害などの他の精神疾患が併存しやすい疾患でもあります。
治療法は従来のうつ病に準じますが、非定型うつ病は再発しやすいので、「規則正しい生活を送る」「身体を動かす」「健康的な食事を取る」などの生活の見直しが重要です。
非定型うつ病やうつ病の症状があると思った場合は、すぐに精神科・心療内科を受診してください。

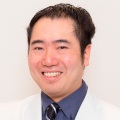
品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。
















