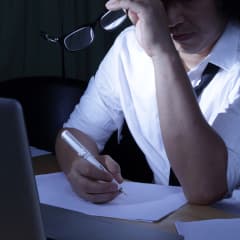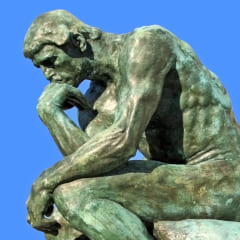不安神経症(全般性不安障害)の症状と治療法、うつ病との関係



「仕事で失敗したらどうしよう」
「テストで赤点をとったらどうしよう」
「明日の朝起きられなかったらどうしよう」
「子供が不審者に狙われたらどうしよう」
このような心配や不安は特別なことではなく、時々このような心配・不安を抱えることはごく普通のことです。
しかし、その心配・不安が常に頭から離れず、仕事や勉強が手につかない、イライラして集中できない、眠れない、肩や背中が痛い、などの不都合が生じている場合、それは健全な心配や不安ではなく病的といえそうです。
この記事では、病的な不安を症状とする《不安症(不安障害)》のなかでも、日常生活上の心配や不安が制御不能なほどに過剰になる《不安神経症(全般性不安障害)》について、症状・原因・治療法、うつ病との関係や違いなどを解説します。
不安症(不安障害)とは
不安や恐怖は、ヒトをはじめとした多くの動物にそなわった普遍的な感情です。目前のハッキリとした脅威に恐怖を感じ、未来や漠然とした脅威には不安を感じます。
古来、不安や恐怖は生き残りに不可欠な感情であり、外敵の接近や危険をいち早く察知するなど、私たちの祖先の生存に役立ってきました。高い所や猛獣を怖いと感じるのはごく自然なことです。
しかし、タイミングが不適切であったり、明らかに過剰であったりする場合、不安や恐怖はその人の日常を乱し、社会生活に悪影響をおよぼしかねません。そういった不適切で病的な不安・恐怖を生じさせる疾患を《不安症(不安障害)》と総称します。不安症は、何に対して不安を感じるかによって、《パニック症(パニック障害)》《社交不安症(社交不安障害)》《限局性恐怖症》など、いくつかの疾患に分類されています。
不安神経症(全般性不安障害)とは
《不安神経症(全般性不安障害)》は不安症の1つで、日常のさまざまなことへの過剰な不安や心配が、長期的に持続するものです。心配のテーマは何かに固定されておらず、1つの心配ごとが終わっても次の新しい心配ごとに不安を抱くということを繰り返します。心配や不安の内容は多様ですが、その内容自体は健康な人が抱く心配と変わりません。ただ、その心配の度合いが生活に影響するほど過剰であり、長期的に持続することが異なります。
不安神経症(全般性不安障害)は、生活の質への影響が大きく、再発率も非常に高い一方で、うつ病などの陰に隠れ見逃されてしまう可能性が高い疾患です。
不安神経症(全般性不安障害)の名称について
まず、《全般性不安障害》は“Generalized Anxiety Disorder”の訳語です。疾患名としての最新の訳語は《全般不安症》です。“Generalized Anxiety Disorder”は“GAD”と省略されます。
次に《不安神経症》は、厳密には全般性不安障害と同じものではありませんが、現在はおよそ同じ意味で使用される言葉です。
そもそも精神疾患は未知の部分が多く、新たな知見や常識の変化などによって、診断基準や名称、分類などが見直されることがたびたびあります。全般性不安障害も、診断基準や分類が繰り返し見直され続けてきた疾患の1つです。
かつて、心理的な要因で生じる心身の機能障害を《神経症》と総称していました。そのころ不安神経症は、神経症のうち不安を症状とする精神疾患のことでした。しかし、1980年の『DSM-Ⅲ』発表時に神経症という病名が廃止され、不安神経症は急性不安の《パニック障害》と、慢性不安の《全般性不安障害》に解体されます。
その後、特徴的で理解しやすいパニック障害は我が国でも定着しましたが、全般性不安障害は診断基準が何度も変更されたこともあって、不安神経症という呼び名が現在でも並行して使用されています。
以降、この記事では、主に《不安神経症(全般性不安障害)》または《全般性不安障害》を用います。
他の不安症との違い
全般性不安障害では、日常のさまざまな懸念(家計、家族の安全、仕事や学業成績のでき、など)が不安や心配の対象になります。全般性不安障害では1つの心配が終わると新しい別のテーマを心配し始めるというように、心配のテーマが次々に移り変わりますが、他の不安症では特定のテーマに限定して不安を感じます。例えば以下のようなものです。
- パニック症(パニック障害):予期しないタイミングで《パニック発作》が起こることへの不安や心配。
- 社交不安症(社交不安障害):飲み会などの交流の場や、プレゼンテーションのように人前で何かをすることへの強い不安や恐怖。
- 限局性恐怖症:特定の対象や状況(犬、クモ、雷、注射針、高所、閉所など)への異常な不安や恐怖。
通常の不安との違い
当然ですが、不安や心配などは、それそのものが病気というわけではありません。病的ではない、通常の心配は制御可能であり、より緊急な出来事が起これば、その心配は後回しにできるため、日常生活に支障はありません。
心配性との違い
「心配性」は小さなことを気にして心配する性質のことです。これは気質や性格であって病気ではありません。
うつ病との違い
うつ病もしばしば不安の症状をもちますが、気分が落ち込み、趣味や活動が楽しめなくなるなどの症状が中核の精神疾患です。全般性不安障害は心配・不安が症状の中心です。なお、後述しますが、うつ病と全般性不安障害は非常によく併存する疾患です。
不安神経症(全般性不安障害)の症状
全般性不安障害では、日常のちょっとした出来事や活動に対して、ずっと(半年以上)、いつも不安で仕方がない状態が続きます。この不安や心配は、心配ごとの実現率や影響に不釣り合いに大きく、そのことを本人も自覚していますが、制御することは困難です。不安のない日よりも不安のある日の方が多く、大変な苦痛を感じており、日常生活に支障をきたします。周囲からは「心配性だな」「気にしすぎでは」と思われがちですが、本人は不安に押しつぶされそうにつらい思いを抱いています。
全般性不安障害では、例えば次のような症状が生じます。
不安神経症(全般性不安障害)の精神症状
全般性不安障害の精神症状には、以下のようなものがあります。
- 制御不能な心配・不安
- 落ち着きのなさ、緊張感、過敏
- 集中力低下、頭が真っ白になる
- 怒りっぽい、イライラする
不安神経症(全般性不安障害)の身体症状
全般性不安障害の身体症状には、以下のようなものがあります。
- 疲労しやすい
- 不眠
- 筋肉の緊張、ふるえ
- 吐き気、下痢
- 動悸、発汗、口の渇き
不安や心配があるときは受診すべきですか?
不安や心配は、誰もが時折抱く自然な感情です。
病的ではない、一般的な心配は制御可能であり、不安や心配に日常生活を支配されるようなことはありません。そのような通常の不安や心配があるだけなら、医療機関にかかる必要はないでしょう。
しかし、心配することが制御できず、次から次へと心配や不安に襲われ、日常生活に支障が出るような場合は病的な心配の可能性があります。そのような場合は、医療機関の受診を検討してください。
不安神経症(全般性不安障害)の原因
全般性不安障害の原因はよくわかっていませんが、遺伝的、生物学的、環境的要因などが相互に複雑に作用して発症していると考えられています。
- 親や兄弟姉妹に全般性不安障害患者がいる場合は発症リスクが高まります。この遺伝的なリスクは、他の不安症や気分障害(特にうつ病)と共通していると考えられています。
- 《神経症傾向》が高い人は、うつ病と同様に、不安症の発症リスクも高いことがわかっています。神経症傾向とは、不安が強く、イライラしやすく、動揺しやすく、心配性で、人目を気にしやすく、衝動的で、ストレスに弱く、感情が不安定という特徴を持つ気質のことです。
- 幼少期の逆境や過保護は、その後の発症のリスクを高めるといわれています。
- 基本的にストレスの多い環境は発症リスクを高めます。
不安神経症(全般性不安障害)の治療
全般性不安障害の治療法は、主に《心理療法》と《薬物療法》によります。さらに最近は、《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》が全般性不安障害に有効であるという報告も増えています。
心理療法
全般性不安障害への代表的な心理療法としては《認知行動療法》や《森田療法》などがあげられます。
- 認知行動療法(CBT):《認知行動療法》は、人の心理面に働きかけることで、否定的な思考パターンを修正し、状態の改善を図る心理療法です。
- 森田療法:《森田療法》は、森田正馬医師が創始した我が国発祥の治療法です。不安や恐怖を、排除すべき特別なものではなく「自然な感情」として受け入れることで、不安にとらわれることなく、自分らしい生き方を実現しようという心理療法です。
薬物療法
全般性不安障害での薬物療法では、《抗うつ薬》や《ベンゾジアゼピン系抗不安薬》が用いられます。抗不安薬は即効性がありますが、耐性と依存の問題から短期間の処方が原則です。
TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
不安神経症(全般性不安障害)への対処
ライフスタイルの改善は、全般性不安障害をはじめとした不安症の発症予防や経過の安定につながります。
ライフスタイルの改善方法には、以下のようなものがあげられます。
- 質の良い睡眠をしっかりとる
- 定期的に休養し、疲れを取る
- アルコールを控える
- カフェインを控える
- 適度に運動する
不安神経症(全般性不安障害)と併存しやすい疾患
全般性不安障害は、気分障害(うつ病や双極性障害など)の併存率が高く、ある調査研究によると、全般性不安障害患者の42.3%がうつ病を併発し、気分障害全体では75.1%も併発したとのことです[4]。
また、多くの場合、全般性不安障害がうつ病の前に発症します。
同じ研究で、パニック障害が24.6%、社交不安障害が26.4%、限局性恐怖症が33.1%併発すると報告されています。
うつ病との併存
前述の通り、全般性不安障害とうつ病は高い割合で併存することがわかっています。
重いうつ病と不安症が併存している場合は不安症の治療がうまくいかないことも多く、基本的にはうつ病の治療を優先します。
不安症状だけではなく、気分の落ち込みを感じるようなら、うつ病を発症している可能性があります。
まとめ
《不安神経症(全般性不安障害)》は《不安症(不安障害)》の1つで、日常のさまざまなことへの過剰な不安や心配が長期的に持続するものです。心配のテーマは固定されておらず、1つの心配ごとが終わっても次の新しい心配ごとに不安を抱くということを繰り返します。
全般性不安障害では、不安や心配にともなって、落ち着きのなさ、集中力の低下、イライラする、筋肉の緊張、不眠などのさまざまな心身の症状も生じます。
全般性不安障害の治療は、主に《心理療法》と《薬物療法》によりますが、最近は《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》が有効であるという報告も増えています。
また、「質の良い睡眠をしっかりとる」「アルコールやカフェインを控える」「適度に運動する」などのライフスタイルの改善も、発症予防や経過の安定につながります。
全般性不安障害は併存症が多く、特にうつ病の併存率が非常に高い疾患です。重いうつ病と不安症が併存している場合は不安症の治療がうまくいかないことも多く、うつ病の治療が必要です。
不安や気分の落ち込みが日常生活に支障をきたしている場合は、医療機関を受診してください。
不安神経症(全般性不安障害)のよくあるご質問
- 毎日ささいなことで不安になってしまいます。これは病気なのでしょうか?
- 不安神経症(全般性不安障害)と診断されました。不安神経症は治るのでしょうか?
- 心配や不安が多いのは性格の問題ではないのでしょうか?
- 毎日ささいなことで不安になってしまいます。これは病気なのでしょうか?
《不安神経症(全般性不安障害)》の可能性が考えられます。毎日、日常のささいなことを心配し、集中力が低下したり、イライラしたりします。疲れやすくなったり、眠れなくなったり、吐き気や下痢になったりすることもあります。早めに精神科・心療内科を受診することをおすすめします。
- 不安神経症(全般性不安障害)と診断されました。不安神経症は治るのでしょうか?
《不安神経症(全般性不安障害)》は、適切な治療やサポートで改善や回復が期待できます。一般的に、どんな病気でも早めに対処することで回復も早まる可能性が高いです。まずは精神科・心療内科にご相談ください。
- 心配や不安が多いのは性格の問題ではないのでしょうか?
他人より心配や不安が多いだけなら性格の可能性もありますが、まったく制御できずに日常生活に支障が出ているようなら、なんらかの精神疾患の可能性が考えられます。精神科・心療内科にご相談ください。

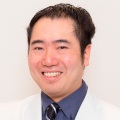
品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。