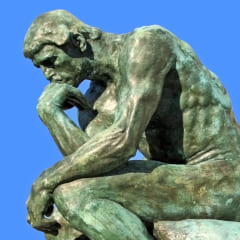抗うつ薬は飲まない方がいい? 種類別の効果と副作用



《抗うつ薬(抗うつ剤)》は、うつ病に対する薬物治療の主役です。現在も改良され続け、治療効果も着実に高まっています。抗うつ薬が廃止されるような未来は考えにくいでしょう。
一方で、服用時の副作用や、中断時の離脱症状(中断症候群)などのはっきりとした短所もあり、これは抗うつ薬治療上、避けては通れない現実です。
しかし、副作用がつらくて治療継続が難しいような場合も、治療をあきらめる必要はありません。うつ病の治療法は薬物療法だけではなく、副作用のほとんど無い治療法もあるからです。
この記事では、抗うつ薬の効果、主な副作用や離脱症状、薬物治療以外のうつ病治療などについて解説します。
抗うつ薬とは
《抗うつ薬(抗うつ剤)》は、気分の落ち込みや興味関心の低下などの、うつ状態の改善を目的として用いられる薬剤の総称です。抗うつ薬は、脳内の《神経伝達物質》のバランスを調整することで改善をはかります。
モノアミンとモノアミン仮説
《モノアミン》とは、《セロトニン》《ノルアドレナリン》《ドーパミン》などの物質の総称です。これらの脳内の神経伝達物質のバランスの乱れが、うつ病の原因であるという仮説が《モノアミン仮説》です。抗うつ薬はこのモノアミン仮説に基づいて作られています。
ちなみに、モノアミンのうち、セロトニンは「落ち込みや不安」、ノルアドレナリンは「意欲や気力」、ドーパミンは「快楽や楽しみ」に関係していると考えられています。
抗うつ薬の種類と特徴
抗うつ薬は、以下に示す1から6の順に開発されました。
- 三環系抗うつ薬(TCA)
- 四環系抗うつ薬(TeCA)
- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
- SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬)
- NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
- S-RIM(セロトニン再取込み/セロトニン受容体モジュレーター)
残念ながら、効果が高く、副作用がまったく無いという完璧な抗うつ薬は存在しません。
古い抗うつ薬は、脳内のターゲット以外に多くの関係のない神経系に作用してしまうため、たくさんの副作用が出ます。基本的には、新しい抗うつ薬ほどターゲットの精度が上がり、効果に対して副作用が抑えられる傾向があります。
薬の効き方や相性などには個人差も出やすく、古いタイプの方がよく効くというケースもあります。
各抗うつ薬の差異は、効果面では小さいですが、副作用面では大きく異なります。薬の効き方、副作用の出方などを見きわめ、患者一人ひとりの状態にあった薬が処方されます。
1.三環系抗うつ薬(TCA)
《三環系抗うつ薬》は、セロトニンやノルアドレナリンを増やす作用にすぐれ、抗うつ効果が強い反面、副作用が多く、QOL(生活の質)への影響が大きいです。口の渇き、便秘、尿閉(尿が出なくなる)、めまい・ふらつき、眠気、体重増加などがよくみられる副作用です。
“TCA”は“Tricyclic Antidepressant”の略称です。
2.四環系抗うつ薬(TeCA)
《四環系抗うつ薬》は、三環系抗うつ薬の大量の副作用を改善するために開発されたものです。三環系と比べて副作用は控えめですが、効果もかなり控えめです。眠気、めまい・ふらつきなどがよくみられる副作用です。抗うつ効果が弱いことと眠気の副作用を利用して、睡眠薬の代わりに処方されることもあります。
“TeCA”は“Tetracyclic Antidepressant”の略称です。
3.SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)
《SSRI》は、セロトニンを増やす作用にすぐれます。三環系抗うつ薬より効果は低いものの、全体的に副作用は少なめです。吐き気、下痢、性機能障害、不眠などがよくみられる副作用です。離脱症状が出やすいです。
“SSRI”は“Selective Serotonin Reuptake Inhibitor”の略称です。
4.SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取込み阻害薬)
《SNRI》は、セロトニンとノルアドレナリンを増やす作用にすぐれ、SSRIよりも効果が期待できる症状の範囲が広いです。全体的に副作用は少なめで、吐き気、下痢、性機能障害、不眠などがよくみられる副作用です。離脱症状が出やすいです。
“SNRI”は“Serotonin Noradrenaline Reuptake Inhibitor”の略称です。
5.NaSSA(ノルアドレナリン作動性・特異的セロトニン作動性抗うつ薬)
《NaSSA》は、四環系抗うつ薬を改良したもので、セロトニンとノルアドレナリンを増やす作用にすぐれます。SSRIで出やすい不眠や性機能障害・胃腸症状が出にくいです。強い眠気、めまい、体重増加などがよくみられる副作用です。
“NaSSA”は“Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant”の略称です。
6.S-RIM(セロトニン再取込み/セロトニン受容体モジュレーター)
《S-RIM》は、我が国では2019年(米国では2013年)に発売になった新しい抗うつ薬です。作用するターゲットがより絞られており、SSRIよりも性機能障害・胃腸症状が出にくく、効果の持続時間が長いため中断症候群が出にくいことが特徴です。副作用は少ないですが、効果も弱めです。吐き気がよくみられる副作用です。
“S-RIM”は“Serotonin Reuptake Inhibitor and Serotonin Modulator”の略称です。
抗うつ薬の副作用
抗うつ薬の、よくある、あるいは重要な副作用としては、以下のようなものがあります。
眠気・だるさ
眠気をもたらす抗うつ薬は、《鎮静系抗うつ薬》と分類されます。三環系・四環系、NaSSAは鎮静系抗うつ薬と呼ばれています。
胃腸症状
吐き気、下痢などの症状で、SSRI・SNRIなどでよくみられます。
口の渇き・便秘・尿閉
尿閉は、尿意があるのに尿が出ない状態のことです。三環系抗うつ薬によくみられる副作用です。
体重増加
抗うつ薬全体が食欲増加→太りやすい傾向に働きますが、三環系・四環系、NaSSAで特によくみられます。
感情鈍麻
感情が平坦化します。ネガティブな気持ちだけではなく、ポジティブな気持ちも鈍くなります。SSRI・SNRIなどでよくみられます。
不眠・アクティベーションシンドローム(賦活症候群)
不安・焦燥・不眠・易刺激性・衝動性などはアクティベーションシンドローム(賦活症候群)と呼ばれ、自傷・自殺企図や暴力行為に進むこともあります。若年層で起こりやすい副作用で、注意が必要な症状の1つです。
セロトニン症候群
脳内の過剰なセロトニン活性のためと考えられています。不安・焦燥、ミオクローヌス(発作的な筋肉の収縮)、発汗、発熱、ふるえ、下痢などが認められます。多くの抗うつ薬で生じますが、SSRIやSNRIなどでみられやすいです。
性機能障害(PSSD)
不整脈・心停止
まれな副作用として、不整脈・心停止があります。三環系抗うつ薬で生じやすいですが、他の抗うつ薬で生じる可能性もゼロではありません。
抗うつ薬の効果・副作用の現れ方
個人差はありますが、抗うつ薬の効果が発現するまでは、早くとも1~2週間がかかります。一方で、副作用は効果を待たずにすぐに現れ始めます。この「効果はないのに副作用はしっかりある」時間差が治療脱落の一因となります。
副作用の多くは一時的なものであり、飲み始めや用量を増やしたときに現れやすく、その後1~2週間程度で落ち着くのが普通です。多くの場合、身体が慣れるに従って副作用が軽減していきますので、我慢できる範囲ならそのまま少し様子を見るのも1つの方法です。不安なようなら主治医に相談しましょう。
なお、継続的に服薬することで副作用が出てくる場合もあります。
どちらにせよ、医師としっかり相談しながら使用することが大切で、自己判断で薬を中断するようなことは避けてください。
抗うつ薬中断症候群
抗うつ薬は基本的に「依存性がなく、中止できる」とされていますが、実際の断薬や減薬は慎重に行う必要があります。急な断薬・減薬時には、「風邪のような症状、不眠、めまい、吐き気、だるさ、しびれや耳鳴りなど」の離脱症状が現れることがあります。これらの離脱症状は《抗うつ薬中断症候群》と呼ばれています。
SSRIを筆頭に、ほとんどの抗うつ薬で、抗うつ薬中断症候群に関する報告があります。
複数の既存研究を解析した論文によると、各研究の離脱症状出現率は27~86%(平均56%)で、離脱症状経験者の46%が重度でした[5]。かなりの割合で英米のガイドラインを逸脱した2週間を超えた離脱を経験しています。
抗うつ薬に限らず、薬は正しい知識、正しい用法で使ってこそ、本来の効果が期待できます。自己判断で中断せずに、必ず医師に相談してください。
うつ病の非薬物療法
抗うつ薬に限らず、同じ薬を使っても、効果にも副作用にも個人差があります。薬物治療では、薬との相性が悪く治療効果を感じられないケースや、副作用に耐えられずに服薬を中断してしまうことも珍しくありません。
最初の抗うつ薬によって寛解(症状がほぼなくなること)できる人は全体の3分の1くらいで、全体の3分の1は抗うつ薬を4種類まで使用しても寛解できなかったという報告もあります[6]。
うつ病治療は薬物療法だけではありません。薬物治療が有効でない場合は特に、薬以外の治療方法にも目を向ける必要があります。
うつ病の非薬物療法には、以下のような治療法があります。
休養・環境調整
《薬物療法》の有無にかかわらず、うつ病治療において休養や環境調整はとても大切なことです。ストレスに満ちた環境では心も休まらず、うつ病の治療どころではありません。《休養》はとにかく休むこと、《環境調整》はストレスフルな環境からストレスの少ない環境に修正することです。
重要なのは、発症前よりもストレスを減らすことです。さらに、一日の中でリラックスできる時間をもうけるなど、意識的に休息をとるようにしましょう。
心理療法・精神療法
《精神療法》《心理療法》ともに“psychotherapy”の訳語で基本的に同じものです。主に心理学的介入によって、患者個人が抱える問題の軽減・解消を目指す治療法を指し、多くの場合は他の治療法と組み合わせて用いられます。
電気けいれん療法(ECT)
《電気けいれん療法(ECT)》は、頭部への通電によって人為的にけいれん発作を誘発することで、精神症状の改善をはかる治療法で、重度のうつ病や統合失調症などに高い治療効果を発揮します。
(けいれん時の)骨折や怪我などのリスクを下げるために、現在では筋弛緩剤と全身麻酔を併用する《修正型電気けいれん療法(m-ECT)》が標準です。
ECTは、重大な副作用として記憶障害があり、また治療時に絶飲食や入院が必要など、他の治療法と比べると実施のハードルは高めです。緊急的なケース(自殺や拒食などの生命の危機がある場合)以外は、重症患者や薬物治療が効かないときに選択されます。
TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》は、磁気を介して脳の特定部位を刺激することで、うつ症状を改善させる治療法です。TMS治療では患部(脳)を直接治療するため、副作用がほとんど無いことが大きな特徴です。副作用がつらくて薬物治療が続けられないという人には、TMS治療はおすすめです。
また、TMS治療は薬物療法とは異なるメカニズムでうつ病に働きかけるので、薬の効果が無い人にも有効である可能性があります。特に2剤目の抗うつ薬も効果が無かった場合は、TMS治療を試す価値は高いでしょう。
まとめ
《抗うつ薬(抗うつ剤)》は、うつ病に対する《薬物治療》の主役ですが、服用時の副作用や、中断時の離脱症状(中断症候群)などの短所もあります。
具体的には、不眠や眠気、ふらつき、体重増加、吐き気、下痢・便秘、性機能障害などさまざまな副作用があります。離脱症状では、風邪のような症状、不眠、めまいなどが現れることがあります。
これらのデメリットを考慮し、現在では《TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)》もうつ病治療の選択肢に加わっています。TMS治療はほとんど副作用が無いため、副作用がつらくて治療継続が難しいような場合は、TMS治療を検討する価値も高いでしょう。
抗うつ薬についてよくあるご質問
- 抗うつ薬は飲まない方がいい?
- 精神科の薬は恐ろしいイメージがあります。怖くありませんか?
- 抗うつ薬の量を増やされました。悪化しているのでしょうか?
- うつ症状が改善しました。抗うつ薬をやめてもいいですか?
- 抗うつ薬はどれくらいの期間、服用を続けるのでしょうか?
- 副作用がつらいです。なんとかなりませんか?
- 抗うつ薬は飲まない方がいい?
抗うつ薬を飲んだ方がいいか、飲まない方がいいかは、症状や状況など患者様一人ひとりに対して判断が必要なことです。一律に「飲んだ方がいい」「飲まない方がいい」ということは言えません。
重要なのは、信頼できる医師と十分に話し合い、納得したうえで治療を受けることです。- 精神科の薬は恐ろしいイメージがあります。怖くありませんか?
精神に作用する、というイメージからか、精神科の薬は必要以上に恐れられているようですが、昔と比べて薬の安全性は高まっています。医師の指示に従って服用している限り、大きな心配をする必要はありません。
- 抗うつ薬の量を増やされました。悪化しているのでしょうか?
抗うつ薬は、強い副作用を避けるために少量から開始し、様子を見ながら少しずつ量を増やしていくのが基本です。悪化しているから量が増えているということではなく、少しずつ薬の量を増やしていくことは一般的なことです。
- うつ症状が改善しました。抗うつ薬をやめてもいいですか?
症状が良くなっているのは薬の効果が出ているからです。良くなったからといって、自己判断でやめたり、薬の量を減らしたりすると、離脱症状が現れたり、うつ病の症状がぶり返したりする可能性があります。薬の調整は、必ず医師と相談して行うようにしてください。
- 抗うつ薬はどれくらいの期間、服用を続けるのでしょうか?
半数の方は、数カ月~半年程度で改善します。症状が改善したあとも、再発予防のために一定期間服薬を維持することが望ましいとされています。症状改善後の服薬期間は、初めての発症の場合で4~9カ月以上、再発の場合は2年以上が目安です。
- 副作用がつらいです。なんとかなりませんか?
抗うつ薬は製品ごとに特色があり、副作用の出方も異なります。薬を変更することで、つらい副作用が軽減できる場合もありますので、医師に相談してください。
また、現在は《TMS治療》とよばれる、副作用のほとんど無い治療もあります。当院でも行っていますので、薬の副作用にお悩みの場合はご相談ください。

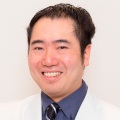
品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。