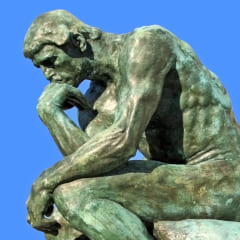女性の更年期障害について~症状・原因と上手な過ごし方、うつ病の可能性~



女性の体は、ライフステージによる、いくつかの段階を経て変化していきます。
思春期に月経を迎え閉経に至るまでには、その時期に応じてバランスよく女性ホルモンを分泌しています。
閉経を迎える頃は「更年期」と呼ばれ、その時期には特有の症状に悩まされる人が多くなります。
更年期とはどのような時期なのか、また更年期障害はどのように克服していけばいいのかお伝えします。
更年期とは
個人差がありますが、更年期は一般的に45~55歳くらいの時期をいいます。排卵のリズムに乱れが起きるようになり、多くの人は50歳前後に閉経します。閉経時期の前後数年は、ホルモン分泌の減少から体調不良の原因になると考えられています。
更年期の女性の体について見ていきましょう。
閉経によってホルモンバランスが乱れる
女性は更年期の時期になると、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が急激に減少します。これは卵巣機能が低下することが原因で、このホルモンバランスの乱れによって心身に現れるさまざまな症状に悩まされる人が多くなります。
またこの更年期の時期は、仕事において大きな責任を背負うことになったり、子供の進学や親の介護などの問題があったり、さまざま大きな心理的な要因も重なることが多くあります。
そのようなストレスによってホルモンバランスはさらに乱れることになります。更年期の体調不良に個人差がみられるのも、このようなことが理由となっています。
更年期障害の症状
更年期に見られる特有の症状と原因


閉経前後の数年には、ホルモンバランスの乱れから、更年期特有の症状に悩まされる人が多くなります。更年期に現れる症状には個人差があり、症状だけみても百種類以上あるといわれます。
ほてりや発汗・疲れを訴える人が多く、他にも冷え・イライラ・めまい・動悸・頭痛などを感じるようになる人もいます。またそのような症状が重なって現れることで、不安感が強くなってしまい、不眠や意欲の低下、抑うつ症状などがみられることもあります。
これらの症状は、自律神経の乱れにも大きな要因があるといわれています。
女性ホルモンの分泌が低下すると、脳が女性ホルモンを分泌させるよう指令を出します。しかし分泌できない状況が続きますので、自律神経が必要以上に働いてしまい、大きな影響を受けてしまうのです。
自律神経失調症と同じような症状がでるのは、このようなことが原因となっているのです。
更年期女性に大事な上手な過ごし方
更年期をどのように過ごせばいいのか見ていきましょう。
更年期の症状はいつまで続くのか
更年期は45~55歳であると考えられ、更年期特有の症状については50代後半くらいには落ち着いてくる人が多くなります。
ただし、症状が始まる時期や落ちついてくる時期も個人差があり、40代前半から症状に悩まされる人もいれば、60代になっても症状に悩まされている人もいます。閉経のタイミングだけではなく、ストレスや環境要因によっても人それぞれ違うからです。
閉経の時期にまったく更年期の症状がなく、親の介護や仕事がひと段落ついたところで急に症状が現れるという人もいるようです。
更年期の上手な過ごし方
更年期は閉経に伴うホルモンバランスの乱れが原因ですから、誰もが通る道であると前向きに捉えておくようにしましょう。
生活を見直し工夫して、上手に過ごすようにします。必要以上に不安になる必要はありません。身体が不調の際にはゆっくりと休むようにして、日々リラックスするように努めます。
日常生活では、「バランスのよい食事」「質のよい睡眠」「適度な運動」を心がけるようにします。食事では普段から栄養バランスに気を付けるようにし、水分もしっかりと補給するようにします。
更年期では自律神経が乱れるため、睡眠の質が下がることがあります。普段から日光を浴びるようにしておくと、脳からメラトニンという物質を分泌させ、夜に眠りやすくなります。寝る前にパソコンやスマホなどを利用することは、脳を刺激し睡眠に悪影響があるため控えておきましょう。
ウォーキングやジョギング、ストレッチなどの適度な運動は、ストレスの発散やリラックス効果、睡眠リズムを整えるのに期待ができます。
うつ病の可能性も? 専門の医療機関に相談を
更年期には、日常生活に大きな影響を与えるほどの症状に悩まされることがあります。これらの症状が更年期障害なのか、更年期のうつ病なのか専門医に相談することが大事です。
更年期の症状には個人差がありますから、治療もその人に合わせて行わねばなりません。
更年期だから仕方がないと、つらい症状を我慢している人もいますが、更年期らしき症状があらわれたら、婦人科や心療内科を早めに受診しましょう。もし、気分が落ち込む、趣味が楽しめない、眠れない、食欲がない、などの症状が2週間以上続き、日常生活に支障が出ている場合は、うつ病を発症している可能性があります。
うつ病は、早期発見・早期対処が早期回復につながります。「うつ病かも……」と不安なときは、セルフチェックの結果にかかわらず、お早めに精神科・心療内科へご相談をお願いします。
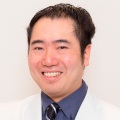
品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。