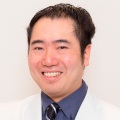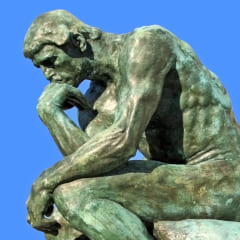過食性障害(むちゃ食い障害)の症状と対処法


- 「いつもより食事のペースが速い」
- 「お腹が空いていなくても食べる」
- 「お腹がいっぱいで苦しい……けど食べる」
- 「たくさん食べているところを人に見られたくない」
- 「食べ過ぎた、と落ち込む」
詰め込むように食べては、それを後悔し、苦悩する──《過食性障害(むちゃ食い障害)》は《摂食障害》の中で最もありふれたタイプですが、人目を忍んで過食(むちゃ食い)するため、周囲に気付かれにくく、受診や治療も遅れがちです。
この記事では、過食性障害(むちゃ食い障害)の症状や特徴、《神経性過食症》や肥満との違い、併存しやすいうつ病との関係や、その治療法などについて解説します。
過食性障害(むちゃ食い障害)とは
《過食性障害(むちゃ食い障害)》とは《摂食障害》の一種で、短時間に大量の食事を満腹以上に食べる過食(むちゃ食い)を何度も繰り返す精神疾患です。《神経性過食症》で見られるような、食後の嘔吐、下剤使用といった不適切な代償行為を伴わないため、体重が増えて肥満するケースが多く見られます。
通常はお腹がすいたら食べ、お腹がいっぱいになったら食事を終えますが、過食中はそのコントロールができず、過食に対して苦しみや羞恥、罪悪感を伴うのが特徴です。
過食性障害は、摂食障害の中でも最も多いタイプで、摂食障害の半数を占めています。
なお、《むちゃ食い障害》と《過食性障害》は、“Binge Eating Disorder”の訳語の違いで、同じものを指します。最新の訳語は《むちゃ食い症》となります。
他の摂食障害との違い
摂食障害とは、拒食や過食など食事の取り方に問題があり、身体・生命や日常生活に大きな影響を及ぼす精神疾患です。主な摂食障害には、《過食性障害》の他に、《神経性やせ症》や《神経性過食症》があります。
これらに共通する心理面の特徴として、「ボディイメージの歪み(自分自身の体重や体形を、過小もしくは過大に評価すること)」や「低い自己評価」などがあげられます。
《神経性やせ症》や《神経性過食症》は、過食した後に、不適切な代償行為(自発的な嘔吐、下剤の乱用、過度な運動など)を伴いますが、《過食性障害》では代償行為を定期的には伴いません。
《神経性やせ症》は、一般に「拒食症」と呼ばれる摂食障害です。極端な食事制限や過度の運動で病的に痩せており、症状によっては過食→吐き出す(代償行為)というパターンを繰り返す場合があります。重症化すると生命にかかわるので、早急に対処する必要があります。
《神経性過食症》は、「大量に食べては吐いてしまう」という世間一般の「過食症」のイメージそのものの摂食障害です。過食しては、「太らないために嘔吐する」などの不適切な代償行為を繰り返します。過食も代償行為も人目につかないように隠れて行う上、体重・体形の変化もあまりないので、過食性障害以上に周囲に気付かれにくい疾患です。
肥満が過食性障害とは限らない
肥満とは、脂肪組織が過剰な状態のことです。
日本の基準ではBMI(ボディマス指数)25以上で肥満、WHO基準(欧米はこちら)ではBMI25以上で過体重、30以上で肥満とされます。
肥満の定義には、過食やボディイメージの歪みのような、行動や心理の異常は要件に含まれていません。カロリー収支(摂取カロリーと消費カロリーの差分)がプラスであれば体重は増えます。たくさん食べ、運動が不足する生活が続けば、必然的に肥満に近づくわけです。
もちろん、肥満自体も健康リスクは高いので、「過食性障害ではないから大丈夫」というわけではありません。肥満に加えて、内臓脂肪の蓄積や特定の健康障害がある状態は、《肥満症》として医学的に減量が必要な状態であると定義されています。
ボディマス指数(body mass index:BMI)について
ボディマス指数(BMI)とは、体重と身長から算出される肥満度を表す指数(単位は「kg/m2」)のことです。計算式は[体重(kg)]÷[身長(m)の2乗]です。例えば身長170cm、体重70kgの場合、「70÷1.72≒24.2」になります。
日本では、標準的なBMIは22.0で、これは統計上、肥満に関連する病気(糖尿病、高血圧、脂質異常症など)にかかりにくい数値とされています。
余談ですが、日本では18.5未満が痩せ、25.0以上が肥満、その間が普通と定義されています。
過食性障害の症状と特徴
過食性障害は、頻繁(週1回以上)に過食エピソードを繰り返すことが本質的な特徴です。
過食エピソードは、エピソード外の時間とはっきり区別される時間帯(通常は2時間以内)に、通常より明らかに多い食事を取ることと定義されます。一日中、だらだらと少しずつ食べ続けるのは過食とはみなされません。過食エピソード中は、食べることをコントロールできず、過食に対して明らかな苦痛・苦悩を伴います。
過食エピソードは、さらに以下のような特徴を3つ以上満たします。
- 通常よりかなり速いペースで食べる
- 満腹でも食べる
- お腹が空いていなくても大量に食べる
- 恥ずかしさから、人目を避けて一人で食べる
- 食べた後に自己嫌悪に陥ったり、落ち込んだり、罪悪感を抱いたりする
過食性障害は不適切な代償行為を(定期的には)伴わない点が一般的な過食症(神経性過食症)と大きく異なります。代償行為を伴わないためBMIが高い傾向があります。WHO(世界保健機関)の調査では、過食性障害患者の30.7%が過体重(BMI25以上30未満)、36.2%が肥満(BMI30以上)と報告されています(注1)。
また、肥満の人が必ずしも過食性障害であるとは限りません。重度肥満者に行われる肥満手術希望者のメンタルヘルスを解析した報告によると、手術希望者の17%が過食性障害にかかっていました(注2)。
なお、過食性障害では、手元に食料が無い場合は購入してでも食べようとするので、経済面にも影響が出ます。
過食性障害の原因
過食性障害の原因はよくわかっていませんが、遺伝的、生物学的、行動的、心理的、社会的など、さまざまな要因が複雑に関連していると考えられています。
具体的には「両親や兄弟姉妹に摂食障害患者がいる」「抑うつ症状があるときの食事制限」「ストレスやネガティブなボディイメージ」などが発症リスクを高める可能性があります。
また、脳画像研究によると、報酬系と呼ばれる衝動性・強迫性に関係する脳内のドーパミン神経回路に変化があることが示唆されています。
過食性障害の併存症
過食性障害では、うつ病や不安症が併存することが多いとされます。
精神的な併存症の割合に関して、不安障害が65%、気分障害(うつ病や双極性障害など)が46%、衝動制御障害(ADHDなど)が43%、物質使用障害が23%という報告があります(注3)。
また、身体的な合併症としては、脂質異常症、高血圧、2型糖尿病、心臓病、メタボリックシンドロームなどがあげられます。
過食性障害とうつ病
前述の通り、過食性障害にはうつ病の併存が多く見られます。
抑うつや不安などのネガティブな感情が過食を引き起こし、過食に伴う罪悪感が抑うつに結び付くというように、相互に影響を与えていると考えられます。
うつ病を治療することで、摂食障害が改善する可能性があります。
過食性障害の治療
過食性障害の治療は、心理療法が中心です。薬の単独使用は推奨されませんが、抗うつ薬と心理療法(認知行動療法)の併用が有用であると多数報告されています。
過食性障害へのTMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)
TMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)とは、磁気による誘導電流で脳の特定部位を刺激する治療法で、うつ病への治療効果が既に認められています。副作用がほとんど無いことが特徴で、麻酔なども不要、普段の生活を続けながら通院治療が可能です。
海外では、過食性障害を含む摂食障害へのTMS治療(経頭蓋磁気刺激治療)の有用性に関する研究や分析が行われています。2022年のメタアナリシス(複数の研究結果を統合的に解析すること)によると、過食性障害と肥満へのTMS治療で、「BMI減少の維持」「不安・抑うつ感情の軽減」に、ある程度の効果を認められたとあります(注4)。
現時点では研究段階であり、過食性障害そのものにTMS治療が効果的であるといえる段階ではありませんが、過食性障害に併存するうつ病・抑うつ症状などに対しては、ある程度の効果が期待できそうです。
まとめ
《過食性障害(むちゃ食い障害)》とは《摂食障害》の一種で、短時間に大量の食事を満腹以上に食べるという過食(むちゃ食い)を何度も繰り返す精神疾患です。《神経性過食症》などと異なり、食後に嘔吐、下剤使用などの不適切な代償行為を伴わないため、体重が増えて肥満するケースが多く見られます。
過食性障害の原因はよくわかっていませんが、遺伝や心理的要因など、さまざまな要因が複雑に関連していると考えられています。
過食性障害では、うつ病や不安症が併存することが多く、他にもさまざまな精神疾患や身体的な合併症を伴います。過食性障害へのTMS治療で「不安・抑うつ感情の軽減」にある程度効果が認められたという解析報告もあり、過食性障害に併存するうつ病・抑うつ症状などに対して、ある程度の効果が期待できそうです。
脚注:
注1)Ronald C Kessler, et al.(2013)"The prevalence and correlates of binge eating disorder in the WHO World Mental Health Surveys", Biol Psychiatry, 73(9), Table 4(参照:2023/4/19)
注2)Aaron J Dawes, et al.(2016)"Mental Health Conditions Among Patients Seeking and Undergoing Bariatric Surgery: A Meta-analysis", JAMA, 315(2), 150-163(参照:2023/4/19)
注3)Leslie Citrome(2017)"Binge-Eating Disorder and Comorbid Conditions: Differential Diagnosis and Implications for Treatment", J Clin Psychiatry, 78(suppl 1)9-13(参照:2023/4/19)
注4)Marco Cavicchioli, et al.(2022)"Is Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (RTMS) a Promising Therapeutic Intervention for Eating Disorders and Obesity? Clinical Considerations Based on a Meta-Analytic Review", Clin Neuropsychiatry, 19(5), 314-327(参照:2023/4/18)
参考文献:
アメリカ精神医学会(2014)『DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル』(高橋三郎・大野裕監訳), 医学書院
久住一郎(編集)(2021)『身体的苦痛症群 解離症群 心身症 食行動症または摂食症群』松下正明監修, (講座 精神疾患の臨床 4), 中山書店
東京都立中部総合精神保健福祉センター(2022)『こころの健康だより』(参照:2023/4/17)
日本肥満学会(編集)(2022)『肥満症診療ガイドライン2022』, ライフサイエンス出版(参照:2023/4/20)
三好美紀「肥満と健康」, 『e-ヘルスネット』(参照:2023/4/18)
山田恒・本山美久仁(2021)「摂食障害の治療ガイドライン」, (摂食障害 最近のトピックス), 『臨床精神医学』, 50(1), 39-44
Cleveland Clinic, "Binge Eating Disorder"(参照:2023/4/20)
Katrin E Giel, et al.(2022)"Binge eating disorder", Nat Rev Dis Primers, 8(1), 16(参照:2023/4/24)
Manal M Badrasawi, Souzan J Zidan(2019)"Binge eating symptoms prevalence and relationship with psychosocial factors among female undergraduate students at Palestine Polytechnic University: a cross-sectional study", J Eat Disord, 33(参照:2023/4/18)
Mayo Clinic, "Binge-eating disorder"(参照:2023/4/17)
Merle Lewer, et al.(2017)"Different Facets of Body Image Disturbance in Binge Eating Disorder: A Review", Nutrients, 9(12), 1294(参照:2023/4/24)
NICE(2020)"Eating disorders: recognition and treatment", Last updated 16 December 2020(参照:2023/4/14)
OWH, "Binge eating disorder"(参照:2023/4/17)
Ronald C Kessler, et al.(2013)"The prevalence and correlates of binge eating disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys", Biol Psychiatry, 73(9), 904-914(参照:2023/4/19)