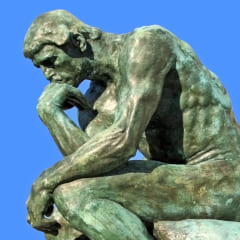場面緘黙(ばめんかんもく)症とは?


場面緘黙症とは
場面緘黙(ばめんかんもく)とは、家族を相手にすれば自由に話ができるのに、幼稚園や保育園、学校などの特定の社会的状況では声を出して話をすることができない状態を指しています。
子供に発症することがほとんどで、性格によるものとして見過ごされてしまいがちです。
そのまま大人になっても症状が持続して、生きにくさを感じながら生活しているといったケースも存在します。
また、稀ではありますが、大人になってから発症するケースもあります。
場面緘黙においては早期発見と対応が必要ではありますが、うまく支援を受けられずに成長してしまうと、症状の改善が遅れてしまうことがあります。
またそれだけではなく、症状による生きにくさが原因となって、うつ病を合併させてしまうことも珍しくないのです。
場面緘黙症と選択性緘黙症
場面緘黙症は人によって症状に違いがありますが、すべての場所で話せないといった症状ではありません。
家庭などでは問題なく話せることができますが、家庭であっても近くに家族以外の人がいる場合には話せなくなってしまうことがあります。
また場所が家庭ではなくても、家族相手であれば話せたり、なじみの人であれば話せることもあります。
場面緘黙症という名称から、幼稚園や保育園、学校など特定の場面によって話せなくなってしまうようなイメージを持ちますが、場面で決まるものではなく、周りの状況などによって決まります。
そのため「選択性緘黙」と呼ばれることもあります。
最新の診断基準においては、「選択性緘黙」の名称が活用されています。
場面緘黙症は性格によるものと誤解されやすい
場面緘黙症は、周りから性格によるものと誤解されやすいですが、そうではありません。
決して人見知りや恥ずかしがりではなく、また親のしつけによるものでもありません。
自分から話す場面を人に聞かれたり、見られたりすることに対して強い恐怖を抱いてしまいます。
場面緘黙症を発症する子供は比較的おとなしい性格の子供が多く、保育園や幼稚園でも問題的な行動が目立つわけではありません。
症状はそのような性格によるものだと、見過ごされてしまうのです。
子供本人からすると、なぜ自分自身が話せなくなってしまうのか分からずにいます。しかし自分の意思によってわざと話さないと誤解されてしまうことも多いのです。場面緘黙症は特定の状況において、1か月以上も声を出して話すことができない状態であることが特徴です。
早期発見や早期支援が、症状の改善にはとても重要になります。
大人の場面緘黙症


大人になってから場面緘黙症が発症することも稀にあります。
また子供のころに症状を見過ごされて、大人になってからも持続しているというケースが多いのではないかと考えられています。
大人の場合であれば、学校や職場において思うように話ができなかったり、体が動かなくなってしまったりすることで、生きにくさを強く感じるようになってしまいます。
学校においては、授業において発言できなかったり、行動しなければならない場面で体が動かなくなったりしてしまいます。
職場においても、業務に必要な発言ができなくなり、作業などにおいてもうまく動作をすることができなくなってしまいます。
場面緘黙には早期発見と対応が必要ですが、適切に対応できなかった場合には、うつ病など二次的な問題を引き起こしてしまうきっかけとなることがあります。
場面緘黙の症状と原因
場面緘黙の症状は人によって大きな差があり、先生などがつきっきりで支援しなければ何もできないという子供もいれば、幼稚園や保育園、学校では話せないだけで仲の良い友達と仲良く遊んでいる子供もいます。
大人の場合も特定の場面で本人の意思に関係なく、話すことができない場合があります。
場面緘黙症の症状
【子供の場合】
- 不安になりやすい
- 緊張しやすい
- 学校でトイレに行きたいと申し出ることができない
- 体育の授業や宿題を提出する時に、動こうと思ってもぎこちなくなってしまう、動けない
- 授業中に指名されても答えることができない、手を挙げることができない など
【大人の場合】
- 不安になりやすい
- 緊張しやすい
- サインなどの動作に時間がかかる
- 指示内容を理解していないのに、聞くことができない
- 上司、同僚の質問に声を出して答えることができない
- 会議での発言、休憩中の雑談ができない
- 慣れない状況で書類を出すことができない など
子供と大人の共通点は「不安になりやすい」、「緊張しやすい」といった点です。
HSP気質などで不安や緊張は過度に感じてしまうとストレスとなり、うつ病などの精神疾患を合併する可能性が少なくはありません。症状の度合いによって、うつ病などの精神疾患を発症している場合は、早めに精神科・心療内科へ受診しましょう。特に青年期以降の方は、うつ病専門クリニックで的確なうつ病検査を受けてみることをおすすめします。
青年期以降の方は
うつ病専門クリニックへご相談を!
場面緘黙症の原因
場面緘黙症の原因は、現時点においては研究段階であり、よく分かっていません。
他の子供と関わる経験がきわめて少ないといった、社会性の未熟さによって発症すると言われることがあります。環境の変化や人間関係などのストレスがきっかけとなって発症する場合も考えられています。
しかし、同じような社会的経験であるとしても必ずしも発症するものではありません。
- 不安になりやすい
- 緊張しやすい
といった生物学的要因がベースとなっていることが多くあります。
何か新しい場面があったときに敏感に反応してしまう行動抑制的な気質は、子供全体の1割程度は存在すると考えられています。
そのような気質を持っている子供が入園や入学といった環境の変化やいじめがきっかけとなって、不安感が急激に高まって発症してしまいます。
そのような状況で話をすることは、自分に注目されてしまうことに強い恐怖を感じてしまうのです。
場面緘黙は周りから性格が原因だと誤解を生じがちで、しばしば家庭環境が問題だと考えられてしまうこともありますが、まったく関係ありません。
場面緘黙症の出現率
場面緘黙症の出現率は研究データによっても差があり、0.1%前後でまれにしか発症しないといったものや、小学校低学年において2%前後の発症率があるというものもあります。
男女比で言いますと、若干女子のほうが出現率が高いと考えられています。
また、大人になって発症することは稀であるとされていますが、具体的な割合については研究段階であり具体的なデータは存在していません。
場面緘黙症からうつ病を合併する?


場面緘黙症は、早期に発見し適切な対応が必要です。しかし実際には見過ごされてしまうことが多く、中には大人になっても改善せずにうつ病を合併させてしまうことも少なくありません。
なぜうつ病を発症させてしまう理由として、「見過ごされやすい」「生きにくさを感じてしまう」ということが言えます。
場面緘黙症の子供はとてもおとなしい子供が多く、幼稚園や保育園、学校においても何か目立って問題が起きるようなことはありません。
おとなしい性格によって話せないのだと捉えられてしまって、場面緘黙症だと気づかれずに過ごしてしまうのです。
しかし本人にとっては、なぜ自分が話せなくなってしまうのか理解できずに、苦しんでいることがほとんどです。
「話したいのに、話せない……」と苦しんでいるにも関わらず、周りからは「なぜ話さないのか」と問われることも多く、理解を得られずに緊張感が高まってしまいます。
いじめを受けてしまうようなこともあります。
そのような状況から腹痛や頭痛といった身体症状が現れることも多く、さらに二次的な問題としてうつ病を発症させてしまうことになってしまうのです。
場面緘黙症にうつ病を併発させてしまった場合には、場面緘黙症の対応と同時に、うつ病に対する治療も必要になります。
ストレスやうつ症状について
ぜひご相談ください!
うつ病の自己診断
うつ病は決して甘えではなく、気の持ちようによって改善するものではありません。
「心の病気」といったイメージがありますが、脳の病気であり適切な治療が必要であるということを理解しておく必要があります。
適切な治療にかかるには、まずは自身もうつ病への理解が必要です。憂うつであったり、睡眠がうまく取れていない、悲観的な気分になるなど一定期間以上感じられる場合は、まずはうつ病の自己診断をしてみましょう。
うつ病には特徴的な症状がいくつもありますが、それらがいくつも重なって引き起こされてしまうことが少なくありません。
気になる症状が2週間以上いくつか継続しているのであれば、うつ病治療専門クリニックである品川メンタルクリニックにご相談ください。
ストレスやうつ症状について
ぜひご相談ください!
参考:
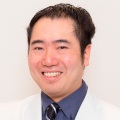
品川メンタルクリニックでは、うつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。