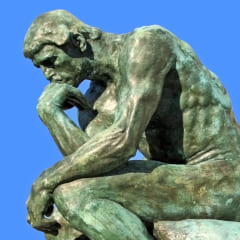認知の歪み~うつ病の人によくある考え方の癖~



「受験に失敗した。もう私の人生は終わりだ」
「企画が没になった。私のアイデアは使い物にならない」
「なんとか内定をもらえた。きっと、私以外の応募が無かったのだろう」
「私はダメ人間だと思う。それこそ、私がダメ人間であるという証拠だ」
「満点がとれなかった。私はもっと努力すべきだった」
何かがうまくいかないとき、何かに失敗したとき、ネガティブな考えが頭に浮かんだり、自己嫌悪や自己批判で落ち込んだりすることはありませんか?
これらは《認知の歪み》が働いているときの典型的な反応で、誰もがこのような考え方の癖を持っています。特にうつ病患者は、この歪みを強く、頻繁に感じることがあります。
この記事では、うつ病の人によくある《認知の歪み》について、10種類のパターンや、歪みの影響、対処法などについて解説します。
認知の歪みとは
《認知の歪み》とは、現実に対し、極端にかたよった解釈をする思考の癖のことです。認知の歪みは誰にでもある自動的な反応で、必ずしも病的なものとは限りません。
一方で、歪み方の頻度や強度・持続性などによっては日常生活に影響し、心身の健康を損なう要因となることがあります。例えば、うつ病などでは症状の一部として認知の歪みが存在することが多く、これらは一般的に治療の対象となりえます。
《認知》とは、外界の情報を知覚、理解、記憶、思考、判断するなどの情報処理の過程全般のことです。私たちは知覚(見る、聞く、触れる、味わう、かぐ)した現実世界の情報を過去の体験や知識をもとに解釈し、その解釈に反応(感情や身体反応、行動)します。
心理学では、認知をさらに深層レベルの《スキーマ》と表層レベルの《自動思考》の2段階に分類します。《スキーマ》とは、経験や知識が蓄積することで形成された思考の枠組みのことで、私たちは、普段は意識せずにこのスキーマを通じて物事を解釈しています。
《自動思考》は、状況に対し、深層のスキーマに基づいて反射的に生じる瞬間的な反応です。自動思考は、熟考や推論の結果ではなく、自動的に湧き出てくる表層的な心のつぶやきです。
認知の歪みは自動思考として現れます。
うつ病でみられる10種類の認知の歪み
《認知行動療法(CBT)》という精神療法の確立につながる研究の中で、アーロン・ベック医師、デビッド・D・バーンズ医師ら研究者たちは、少なくとも10種類の認知の歪みが存在することを明らかにしています。例えばデビッド・D・バーンズ医師は、うつ病で一般的にみられる認知の歪みとして、以下の10種類をあげています。
1.全か無か思考
《全か無か思考》は、ものごとを「白か黒か」「成功か失敗か」の両極端に分ける考え方です。黒と白の間に灰色があるように、状況も普通は連続的です。しかし、全か無か思考にとらわれると、例えばわずかなミスがあるだけで「もうだめだ」と完全な失敗と考えてしまいます。
- テストの結果が90点のときに、「満点でなければ意味はない」と考える。
- 受験に失敗したときに「もう私の人生は終わりだ」と考える。
- 営業成績が達成できないときに「私は無能だ」と考える。
このような考え方は、完全主義が基盤になっています。ほんの小さな失敗に、自分はダメで無価値な人間だと思い込むため、わずかな失敗も恐れるようになります。
《全か無か思考》は、《白黒思考》《二分割思考》とも呼ばれます。
2.一般化のしすぎ
《一般化のしすぎ》は、たった1つの良くない出来事から、将来のすべての出来事が否定的なものになると結論付ける考え方です。一般化のしすぎにおちいると、「いつも」「決して」「どうせ」「絶対に」などが(否定的な使い方で)言葉の端々によく現れます。
- 商談に失敗したときに「私には、商談をまとめることはできない」と考える。
- 告白してふられたときに「私と付き合いたいと思う人は一人もいない」と考える。
- 作った企画が没になったときに「私のアイデアは箸にも棒にもかからない無価値なものである」と考える。
《一般化のしすぎ》は《過度の一般化》ともいわれます。
3.心のフィルター
《心のフィルター》は、わずか1つの良くないことにとらわれて、そればかりくよくよと考え、現実を真正面から見ることができなくなる考え方です。
- 新製品は品切れを起こすくらいよく売れているが、1件の批判的な口コミを見つけた。きっと他の良い口コミはただの社交辞令で、批判的な口コミこそが本音である。新製品を売り出したのは失敗だった。
- 久しぶりに友人との飲み会を楽しんだが、Eさんだけは私とあいさつも交わさなかった。Eさんは私を嫌っているにちがいない。私は参加するべきではなかった。
《心のフィルター》は《選択的抽出》ともいわれます。
4.マイナス化思考
《マイナス化思考》は、何でもないことや良い出来事を、悪い出来事にすり替えてしまう考え方です。良い出来事を無視するだけではなく、悪い出来事であると反転してとらえてしまうため、毎日が常にマイナスのものになってしまいます。
- 試験に合格したのに「単に運が良かっただけ」と考える。
- 就職の内定をもらったときに「きっと、私以外に応募が無かったのだ」と考える。
5.結論の飛躍
《結論の飛躍》は、根拠もないのに悲観的な結論を導く考え方です。《心の読みすぎ》と《先読みの誤り》の2種類があります。
- 心の読みすぎ:ある人が否定的に反応したと早とちりします。
休日に友人とすれちがったが、友人は目も合わせず立ち去った。実際は他のことに気を取られてあなたに気付かなかっただけかもしれないのに、「友人が私を無視した。私は嫌われているんだ」と考える。 - 先読みの誤り:事態は必ず悪くなると確信します。
翌日、「無視した。嫌われた」と思い込み、友人に声をかけることができない。「声をかけると嫌な顔をされるのでは」と不安になるからだ。
6.拡大解釈と過小評価
《拡大解釈と過小評価》は、自分の失敗や短所は過大評価し、成功や長所は過小評価する考え方です。小さな失敗を大惨事に、大きな成功をたいしたことがないととらえます。
- 上司から報告書の書き損じを指摘された。「私は書類1つ満足に書けない」と考える。
- コンクールで入賞できたのは、「先生の教え方がうまかったから」「幸運だったから」と考える。
7.感情的決めつけ
《感情的決めつけ》では、自分の感情が、あたかも事実を証明する証拠であると考えてしまいます。状況や証拠が正しくないことを示していても、「自分がそう感じている。だから、それは本当のことだ」と、おかまいなしです。
- 「私はダメ人間だと思う。それこそが私がダメ人間である証拠だ」
- 「何の希望もないように思う。だから私の未来に希望はない」
8.すべき思考
《すべき思考》があると、何かをやるときに、「~すべき」「~すべきではない」と考えます。それは状況を考慮しない、例外のない鉄則で、そうしないと罰でも受けるかのように感じています。
- テストで満点を取るのは当然のことなので、そのために私は寝る間を惜しんで最大限努力すべきである。
- 90点しか取れなかった。私はもっと勉強すべきだった。
- 健康的な睡眠のために、毎晩午後11時までにベッドに入るべきである。
すべき思考を他人に対してもあてはめて、勝手に怒りや葛藤を抱え込むこともあります。
9.レッテル貼り
《レッテル貼り》は、特定の特徴を取り上げ、その人の全体に一般化する考え方です。例えば何かに失敗したときに、失敗そのものではなく(失敗した)自分自身に目を向け、「自分は落伍者だ」と自分自身にレッテルを貼ります。
- 「契約が取れなかった。私は社会人失格だ」
- 「数学のテストが赤点だった。私は頭が悪い」
- 「遅刻してしまった。私は無責任な人間だ」
テストの赤点が示すのは、「もっと勉強する必要がある」ということであって、落伍者であるということではありません。1度の遅刻が無責任であることを証明するわけでもありません。
感情的で偏見に満ちたレッテルを他人に貼る場合もあります。数個の特徴から誰かの全体を推し量るというのは無謀で無責任な挑戦です。
10.個人化
《個人化》とは、自分自身がコントロールできない出来事に対し、自分自身が責任を負っているという考えです。個人化は、しばしば無用な罪悪感を招きます。
- 子供の成績を見て「この子の成績が悪いのは、親である私のせいだ」と考える。
- 通りすがりに舌打ちしている人を見て、「私が何かやってしまったからだ」と考える。
- 電車が遅れて約束の時間に遅れてしまった。「私がもっと早く向かっていれば遅れなかったのに」と考える。
認知の歪みがあるときは医療機関にかかるべきですか?
実のところ、認知の歪み自体は、それほど特別なものではなく、誰もが日常生活の中で経験しているものです。認知の歪みを感じたからといって、すぐに医療機関にかかる必要はありません。しかし、高頻度、あるいは歪みが深刻な場合は気を付ける必要があります。
- 頻繁な認知の歪みが、思考や感情に影響していると感じる
- 認知の歪みによって、日常生活、人間関係、仕事などに悪影響を与えている
- 気分の落ち込み、食欲不振など、認知の歪み以外にも症状がある
もし、上記のような状態・症状が2週間以上続くような場合は、医療機関に相談することをおすすめします。
ただし、認知の歪みは自動的、無意識的な思考のため、その存在を自覚できない可能性があります。ひとまずは日常生活に支障が出ているような場合は、医療機関の受診を検討してください。遠慮は不要です。あなたの健康を優先してください。
認知の歪みによる影響
私たちは日常的に、「見る・聞く・触れる・味わう・かぐ」といった感覚を通じて現実世界を知覚しています。そこには、良いこと・悪いこと・意味のないこと・関係のないことなど、さまざまな情報が含まれています。
私たちはこれら一次的な情報を、過去の体験や知識をもとに解釈し、その解釈に反応して悲しみ・楽しみ・喜び・苦しみといった感情を抱きます。
認知の歪みは、この「解釈する」というプロセスに影響します。
- 証拠の無い思い込みを信じる
- 明らかな証拠を無視する
- 他者の意見や別の視点、他の解釈を受け入れることが難しい
こうした認知の歪みは、単に誤った意思決定を招くだけではなく、うつ病を始めとするさまざまな精神的問題の発症・維持・悪化・再発に関与する可能性があります。
具体的には、以下のような疾患や状態に関連するとされています。
- うつ病
- 不安障害(パニック障害・全般性不安障害・社交不安障害など)
- パーソナリティ障害
- 依存症
- PTSD(心的外傷後ストレス障害)
- 摂食障害
- 低い自己評価
- 自殺リスクの増加
認知の歪みへの対処法
認知の歪みとうつ病は、お互いに影響しあうことが分かっています。うつ病にかかると否定的な考えに傾きやすくなり、その否定的な考えがうつ病を悪化させる可能性があります。まさに悪循環です。
一般的に認知の歪みはその存在に気付きにくく、まずは歪みの存在に気付くことが重要です。
思考の偏りに気付く
自分自身が抱く、抑うつや不安、否定的な感情や思考に気付くようにしましょう。日記をつける、マインドフルネスを実践するなどは、自分自身の考えの癖を知り、思考を客観視するために役立つ可能性があります。
認知の歪みの影響を認識する
上述の通り、こうした認知の歪みは、単に誤った意思決定を招くだけではなく、うつ病を始めとするさまざまな精神的問題の発症・維持・悪化・再発に関与する可能性があります。
思考の変化に挑戦する
認知の歪みに気付き、それが問題を引き起こしていると認識した場合は、積極的に変えるように努めます。
専門家に相談する
認知の歪みが、うつ病などの精神疾患の原因になっている可能性がある場合は、医療機関に相談しましょう。医師はあなたの認知の歪みや不調の状態・原因を探り、適切な治療を提案します。
受診するかどうか悩むような場合は、セルフチェックの利用などもよいでしょう。
とはいえ、うつ病をはじめ精神疾患は早期発見・早期対処が重要ですので、自分が何かの病気かもしれないと不安になるようなら、セルフチェックの結果に関係なく医療機関に相談してください。
まとめ
《認知の歪み》とは、現実に対し、極端にかたよった解釈をする思考の癖のことです。
認知の歪みは誰にでもある自動的な反応で、必ずしも病的なものとは限りませんが、歪み方の頻度や強度・持続性などによっては日常生活に影響し、心身の健康を損なう要因となることがあります。
認知の歪みは、《認知行動療法(CBT)》という精神療法の確立につながる研究の中で、少なくとも10種類が存在することが明らかになっています。デビッド・D・バーンズ医師は、うつ病で一般的にみられる認知の歪みとして《全か無か思考》《一般化のしすぎ》《心のフィルター》《マイナス化思考》《結論の飛躍》《拡大解釈と過小評価》《感情的決めつけ》《すべき思考》《レッテル貼り》《個人化》の10個をあげています。
認知の歪みは、単に誤った意思決定の要因になるだけではなく、うつ病を始めとするさまざまな精神的問題の発症・維持・悪化・再発に関与する可能性があります。
認知の歪み自体は、それほど特別なものではなく、誰もが日常生活の中で経験するものです。認知の歪みを感じたからといって、すぐに医療機関にかかる必要はありません。
しかし、高頻度、あるいは歪みが深刻で日常生活に悪影響があるような場合は医療機関の受診を検討してください。

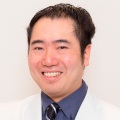
品川メンタルクリニックはうつ病かどうかが分かる「光トポグラフィー検査」や薬を使わない新たなうつ病治療「磁気刺激治療(TMS)」を行っております。
うつ病の状態が悪化する前に、ぜひお気軽にご相談ください。