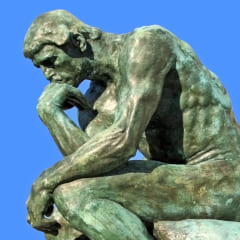大切な人のうつ病

「最近、よく眠れていないようだ」
「食が進まず、痩せてきた」
「新聞やテレビを見なくなった」
「会社や学校に行くのを渋る」
「イライラしている」
「趣味をしなくなった」
《うつ病》はさまざまな症状が現れますが、発見や治療は遅れがちです。心理的な症状は自覚しにくく、身体症状を自覚しても自分の弱さと思い込んで自分を責めるだけで、うつ病のせいだとは思いません。
病気のはずがないと否定しがちな本人よりも、元気がないと心配するご家族が先に気付くことも少なくありません。
うつ病は、病気の気付きにも、その後の支えにも、ご家族やパートナーの存在がとても大きな意味を持ちます。
このページでは、大切な人のうつ病にいかに気付き、どう医療機関へつないで、どのように治療を支えれば良いのかについて解説します。
うつ病そのものが知りたい方は以下のページも併せてご覧ください。
うつ病の兆候(サイン)
うつ病にはさまざまな症状がありますが、目を向けるべきは変化、つまりは「以前と比べて違っているかどうか」です。
一般に睡眠・食事・会話や表情などに現れる変化は外から分かりやすい変化です。特に長い時間を共有するご家族は、その変化に気付く可能性が高いといえるでしょう。
次のような様子(症状)が一日中、ほとんど毎日、2週間以上続いているような場合は、うつ病を発症している可能性があります。これらの症状は、少しずつ時間をかけて現れるというよりも、次々にいくつも現れることが普通です。
寝付けない、変な時間に目が覚める
寝付きが悪くなる《入眠困難》、夜中に目覚めた後に眠れなくなる《中途覚醒》、起床予定の何時間も前に目覚めてしまう《早朝覚醒》といった《不眠》は、うつ病でよく見られる症状です。朝早くに目覚める《早朝覚醒》は、うつ病に特徴的な症状の1つです。
逆にいくら眠っても眠気も疲れも取れず、いくらでも寝てしまう《過眠》になる場合もあります。
食が進まない、食事がおいしくない
食欲が低下し、空腹感があっても食べたいと思わなくなります。無理に胃に詰め込むことはできますが、好きなものもおいしいと感じず、しまいには味も感じなくなります。実際に食が細くなった場合は、目に見えて痩せることもあります。
また、逆に食事量が増えて体重が増加することもあります。
だらしない印象になった
入浴や身だしなみを整えるような、日常の行為ができなくなります。必要性を感じながらも活力が湧かずにできなくなっています。以前はできていた普通の行動が、本人にとってはとても疲れる行動になり、結果としてできなくなるというわけです。
ミスが増えた、成績が落ちた
集中力が低下し、仕事のミスが増えます。子供の場合は急激に成績が低下する場合があります。
思考力・決断力が低下し、優柔不断になります。
笑顔がなくなった、趣味をしなくなった
以前は楽しんでいたことが楽しめなくなります。感情の起伏が失われ、表情に乏しく、ぼーっとしている印象が強くなります。以前は熱中していた趣味をしなくなり、新聞やテレビも見なくなります。
自覚は無くとも、私たちは習慣の中に興味関心を忍ばせています。それらに関心が向かわなくなることで、ぼんやりしている時間が増えます。
口が重い、動きが重い
声が小さくなり、会話の量も減ります。しゃべり方も感情がこもらずのっぺりした印象です。
身体を動かすのが大変で、トボトボ歩くなど、目に見えて動きが鈍くなります。
疲れやすいというよりは常に疲れている感じです。
落ち込んでいる、ふさぎ込んでいる
表情が暗く、見るからに元気がありません。肩を落とし、うつむきがちで、猫背気味になっていることもあります。
普通ならうれしかったり気が晴れたりするようなことがあっても、ほとんど反応がありません。
落ち着かず、イライラしている
落ち着きなく、イライラと攻撃的になることがあります。特に若年層のうつ病では、この傾向が強いです。
医療機関に連れていく
うつ病は放っておいてもすぐに良くなる病気ではありません。治療しなければ長く苦しむ場合があります。うつ病の疑いがある場合は、早めに医療機関にかかりましょう。
受診はどこに?
うつ病の治療は精神科や心療内科で行っています。
症状が非常に重く、自殺願望がある場合や、食事がとれず体重減少が著しい場合など、生命に危険が迫っているときは、入院設備がある医療機関がおすすめです。
ともあれ、状態を知るためにも医療機関にかかることが重要です。どうしても精神科や心療内科の受診に抵抗が強い場合には、まずはかかりつけ医を受診してください。
「病院に行きたくない」という場合は?
うつ病が疑われる場合でも、本人がそれを認めず、医療機関──特に精神科にかかりたがらない場合があります。抵抗が強くとも、嘘をついて医療機関に連れて行ってはいけません。
「買い物に行こう」など、弁解しようのない噓で病院に連れて行くようなことは信頼関係を壊し、その後にさまざまな支障をきたします。精神科と伝えず、医療機関とだけ告げるような曖昧な表現は、(当事者の性格にもよりますが)あまり問題にならないようです。
どうしても受診への抵抗が強い場合は行政機関(保健所や精神保健福祉センターなど)を頼ることも視野に入れてください。
- 厚生労働省「全国の精神保健福祉センター」
- 厚生労働省「保健所管轄区域案内」
ご家族の付き添い
うつ病によって患者様本人の判断力が低下している場合も多いため、うつ病が疑われる場合は、できればご家族も付き添われると安心です。
うつ病をはじめとした精神疾患では特に、ご家族からの情報も診断の大きな材料になります。
治療開始後の注意点
うつ病の治療を開始したあとは、以下のような点に気を付けてください。
言葉のかけ方
ご家族は、無理に明るく振る舞ったり、過剰に気を使ったりする必要はありません。無理に取り繕うのは、患者様本人にも負担になり、「迷惑をかけている」と自責の念を持たせます。そうした変化はストレスになり、当事者の回復を妨げます。普段通りに接しましょう。
会話も改まったものは必要なく、「おはよう」のあいさつから天気の話題など、普段の何気ない会話を心がけます。返事がない、表情も変わらない、聞いているのかどうかも分からない──こういった反応(無反応)に、気になったり、時に不快に感じたりすることもあるかもしれません。しかし、これらは病気のせいですから、気にし過ぎないでください。
話すことが見つからないなら無理に話す必要はなく、ただ一緒の空間で一緒の時間を過ごすだけでも構いません。別に同じ部屋で向き合い続ける必要もありません。お互いに存在を感じ、必要なときに声をかけられるような距離にいれば十分です。
決断は求めず、重要な決断は先延ばしに
判断力や決断力が鈍っているため、「今日の夕食はどうする?」程度の決断すら負担になる場合があります。「今日は餃子にしようか」などと、具体的に提案してあげましょう。
また、否定的な考えも強いため、退職や転職のような大きな決断は、病気が落ち着くまで延期しましょう。
原因を追究しない
うつ病の原因は、現在もはっきりと解明されているわけではありません。よくわかっていないものを追究しても、意味が無いどころか、むしろ当事者を追い詰めるなど悪い影響ばかりです。
治療初期(急性期)の注意点
治療初期、症状が重いうちは、はげましや気分転換は逆効果になりがちです。
うつ病患者の多くは頑張りすぎてうつ病になっているため、これ以上頑張りようがありません。また、気分転換とは要するに変化です。変化はそれ自体がストレスとなりますので、症状の重い時期には避けるべきです。ただそばで見守るだけで十分です。
重要なのは「休養」を取らせることです。十分な睡眠で脳を休ませましょう。
本当に苦しい治療の最初期は、一日中寝ていても問題ありません(生活のリズムを維持構築するためのエネルギーも枯渇しています)が、その時期を過ぎれば、(様子を見ながら徐々に)生活のリズムを整えていきます。
回復期の注意点
社会復帰のためには、うつ病の症状がおさまっていることと、生活が規則正しいリズムに戻っていることが必要です。生活のリズムの改善のポイントは睡眠にあります。睡眠はできるだけ規則正しく取るようにします。一日中、布団の中で過ごすような生活は、睡眠の質を悪化させ、回復をさらに遅れさせます。決まった時間に起床することで生活のリズムを整えます。
また、食事も重要です。食欲が無くとも、例え少量でも、一日三食、できる限り決まった時間に食事を取るようにします。
この時期はまだまだ症状が不安定で、良くなったり悪くなったりと波があるのが普通です。無理をしすぎないように、頑張りすぎているときには適度にブレーキをかけてあげるのも、ご家族が手助けしやすい部分だと思います。
自殺を防ぐ

うつ病患者の自殺が多いのは、発症直後と、ある程度回復してからです。自殺の実行にもエネルギーが必要なので、最も重症な時期の自殺は多くはありません。
自殺をほのめかされたときは、ご家族は「死にたいほどつらい」という気持ちを受け止めた上で、「死なないでほしい」と頼んでください。もともと責任感の強い患者様が、頼まれることで自殺を思いとどまるというケースはよくあります。
「死にたい」「死んだら楽になる」という言葉の裏には、「生きたい」という気持ち(願い、希望)が潜んでいます。よく「死にたいという人ほど死なない」といわれますが、これは誤った思い込みです。
「死にたい」というのは、死に希望を見出しているわけではありません。現実の絶望から逃れるために、死に救いを求めているのです。このニュアンスの違いはとても重要です。
共倒れしないために
ご家族は患者様の大きな支えとなり得ますが、うつ病当事者を支え続けるのは、正直なところ簡単なことではありません。
ネガティブな言動ばかりの患者様にストレスを感じるのは当然のことです。それが病気によるものとわかっていても受け入れがたく感じるのも仕方のないことです。事情をよく知らない第三者が訳知り顔でご家族を責めるなど、本当につらく悲しく苦しい思いをすることもあります。
葛藤があるのは何も不思議なことではなく、むしろ当たり前のことです。そこに罪悪感を抱く必要はありません。
知識を持ち、訓練を積み、しかも第三者的な立場でしかない医療者ですら、それが例え病気の症状だとわかってはいても、正面からネガティブな言葉を投げつけられたりすれば穏やかな心ではいられません。当事者と真正面から取り組むことになる、一般のご家族の方はましてや、でしょう。
共倒れしないためにも自分たちだけで何とかしようと抱え込まないでください。もしまだなら一刻も早く医療機関や適切な支援にかかってください。決して、自分たちだけで支えようと気負わないでください。
ご自身がうつ病にならないためにも、愚痴が言える友人や、当事者ではない他の家族や親族、あるいは医師やカウンセラーなど、心身をむしばむストレスを受け止めてくれる協力者の存在は不可欠といえます。
まとめ
ご家族のうつ病とのかかわりは、病気への気付きから始まります。
病気の疑いがある場合は、医療機関にかかる必要があります。可能なら同行して医療者に直接つなげると安心です。
ご家族のうつ病を支えるのは実際には容易なことではありません。共倒れしないためにも、専門家の助けを得るなど、自分たちだけで抱え込まないようにしましょう。

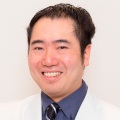
関連する記事
-

精神医学と心理学
うつ病になりかけ・始まりのサイン~初期症状への対処法~
夜中に何度も目覚める、どうしようもない悲しみやむなしさに襲われる、身体に痛みを感じる、わけもなく涙が出る──これらの症状は、うつ病になりかけのサインかもしれません。うつ病のサインとなる、初期に現れやすい症状と対処法を解説します。
-

精神医学と心理学
その不眠はうつ病の症状かも?
寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚める、朝早くに目覚めるなどの《不眠》は、成人の3分の1が悩むありふれた睡眠の問題で、《うつ病》の8割以上の人に現れる症状です。不眠の症状やうつ病との関係、原因や対処法、受診の目安などについて解説します。
-

精神医学と心理学
「お風呂がめんどくさい」のはうつ病だから?
疲れている時、忙しい時にお風呂を面倒に感じるのは仕方がありませんが、気力がわかずに何日も入浴できなくなった場合は、うつ病の可能性があります。うつ病患者がお風呂に入れなくなる理由と対処法、入浴のメリットについて解説します。
-

精神医学と心理学
イライラはうつ病のサインかもしれない~その原因と対処法~
うつ病では、イライラと怒りっぽく、攻撃的になることがあります。それほど珍しい症状ではありませんが、敵意や怒り発作など、人間関係を破壊しかねない厄介な症状です。うつ病のイライラの原因と対処法などを解説します。
-

精神医学と心理学
うつ病の人は「誰もわかってくれない」と苦悩している
うつ病は周囲の人に「怠けている」「甘えている」「やる気がない」と誤解されやすく、本人が周囲に相談できずに悩んでいることも多い病気です。家族や職場の人がうつ病になったときに、周りの人が何に気を付けて、どのように接するべきかについて解説します。
-

精神医学と心理学
うつ病はうつるの? 情動感染とメンタルヘルス
インフルエンザや普通の風邪のように、《うつ病》が細菌やウィルスで伝染するということはありませんが、伝染しているように見えることがあります。なぜ伝染しているように見えるのか、どう自分を守るべきなのかなどについて解説します。